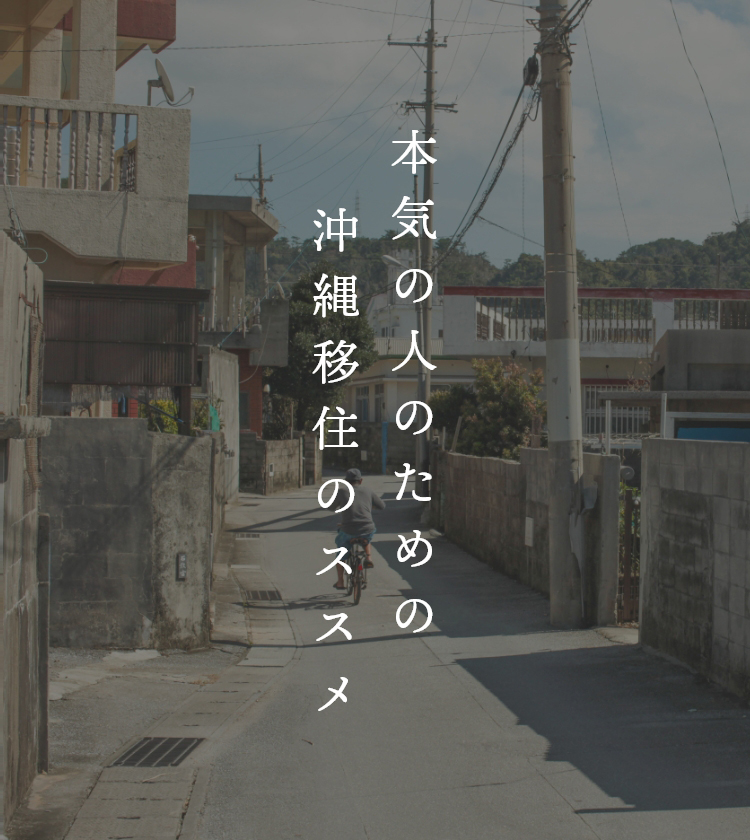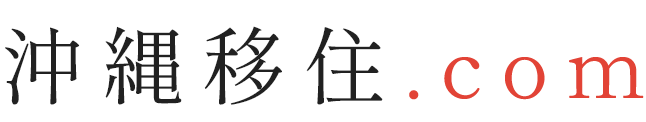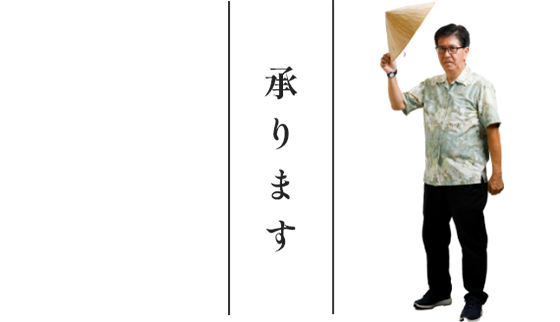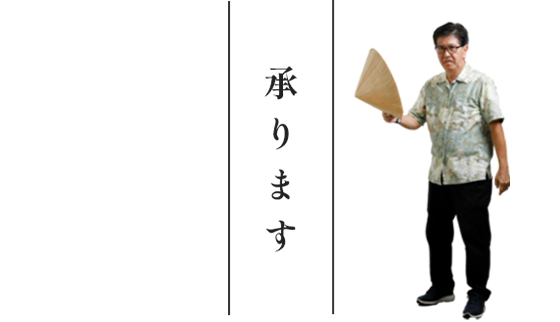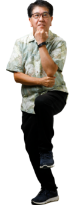【成功する沖縄移住】お彼岸の墓参りが掟破りなのはなぜか?
昨日はお彼岸の中日だったので、やんばるへ墓参りに行ってきた。しかし、沖縄でお彼岸に墓参りするのは少数派というか、ある意味掟破りである。なぜか、解説してみよう。
メニュー
沖縄ではお彼岸に墓参りをしない
お彼岸といえば、日本ではお墓に参る時期とされている。しかし、沖縄においては、お彼岸に墓参りをする習慣はほとんどない。
通常は4月のシーミー(清明祭)、または1月のジュウルクニチ(十六日祭)のいずれかに行う。
そして、墓参りは原則年1回である。筆者の家はこの点に違和感を覚えていた。
そこで本土風のお彼岸を採用し、年2回できるようにしたのである。

筆者の家の墓はデザインも沖縄っぽくなく、どちらかというと本土風に造った。だからお彼岸に墓参りをしても不自然ではない(はず)。
むやみにお墓へ行かない四つの理由
ではなぜ、ウチナーンチュは年に1回しか墓参りをしないのか。それは、沖縄ではむやみに墓に行ってはならないと考えられているからであるが、その理由は諸説ある。
一つ目は、頻繁に墓参りをすると、周囲の墓に眠る他のご先祖が寂しがる。
二つ目は、むやみにお墓へ行くと、良くない霊に取り憑かれやすくなる。
三つ目は、風葬時代の名残が影響しているとする説。かつての沖縄では、亡くなった人が葬られた直後は、お墓周辺に強烈な臭気が漂っていたため、頻繁に訪れることが避けられていた。
四つ目は、昔の墓は山の中のうっそうとした場所に造られることが多く、時にはハブが潜んでいることもあり、危険を伴った。

昔風の風葬墓。ハブや悪霊がウロウロし、すさまじい死臭が漂う場所なら、やはりむやみに行かない方がよいのかも。
沖縄では墓参りをせず仏壇を拝む
では、沖縄ではお彼岸にはなにもしないのかというとそうでもない。沖縄にも本土からお彼岸の風習が伝わったのはたしかである。
しかし、それがそのまま定着することなく、沖縄独自の形に変化したのである。
どうなったかというと、お彼岸に墓参りをせず、仏壇を拝むようになったのだ。
沖縄には「お墓と仏壇はつながっている」という考え方があり、お墓へ行くことによるリスクを考えれば、仏壇を拝むことで代替するのも合理的といえる。
加えて、沖縄にはシーミーやジュウルクニチーがあり、旧盆前には七夕にお墓掃除も行う。
シーミーと時期の近い春のお彼岸や、旧盆直後の秋のお彼岸にまで墓参りをするのは、やりすぎと考えられたのかもしれない。

筆者の家の墓は、このようなお墓団地にあるので、悪霊はともかく、ハブがうじゃうじゃいるようなところではない。なので行きやすいのである。
本土よりも丁寧な供養
墓参りをするか仏壇を拝むかという違いはあるものの、ご先祖への想いが軽視されることはない。
むしろ、本土のお彼岸よりも手厚い供養が行われるといえる。
沖縄の彼岸の入りには、屋敷を守る神々に感謝を捧げる「屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)」が行われるのも特徴的だ。
まず、重箱料理を準備する。これは「ウサンミ」と呼ばれる。また、果物、お菓子、お餅、お茶などを供え、線香を焚いて「ウートートー」する。
その後、供え物を分け、ヒヌカン(火の神)など屋敷内の神々を拝む。最後にウチカビ(あの世のお金)を燃やす。
こうしたお彼岸の儀式は、旧盆などと大きく変わらない。墓参りこそしないものの、心を込めた供養が行われる。
ご先祖とのつながりを再確認し、家族の健康と繁栄を願う日であることに変わりはない。

記事とはあまり関係ないが、こちらは筆者の家の墓に隣接する教会の納骨堂で、信者の共同墓である。シーミー、ジュウルクニチ、お彼岸、どんなときにお参りするのかいつも疑問だ。
同じカテゴリーの人気記事
2026/01/20
【成功する沖縄移住】サブスクで街歩き動画配信中!
2025/12/11
【成功する沖縄移住】今帰仁村の生家をリノベ中!
2025/11/27
【成功する沖縄移住】今年は暴風警報が出ていない!
人気の記事 (note)
吉田 直人 よしだ なおひと
沖縄県今帰仁村生まれ。19歳まで沖縄で過ごし、20代は横浜に住む。大学卒業後は都内の出版社に勤務し、30代でフリーランスとなって沖縄に戻る。その後はライター兼編集者として活動。沖縄移住に関する本など多数の著作あり。
著作の紹介
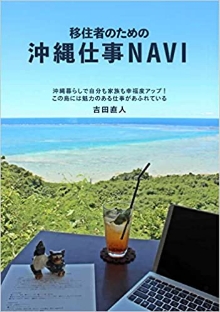
沖縄で仕事を探す! 移住者のための沖縄仕事NAVI
沖縄移住を成功させるカギ、それは仕事だ! 沖縄における就職事情と、仕事をゲットするコツを伝授。
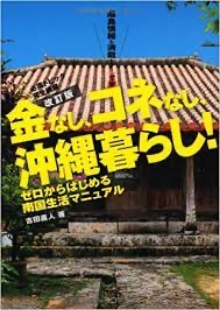
沖縄移住のバイブル! 金なし、コネなし、沖縄暮らし!
暮らしも遊びも人付き合いも、生活のすべてを網羅した面白本。ウチナーンチュが本音で語る沖縄暮らしの真実。
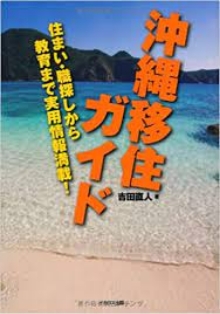
沖縄暮らしのAtoZ 沖縄移住ガイド 住まい・職探しから教育まで実用情報満載!
どこに住むか、どう働くか、子どもの教育をどうするか・・・客観的視点から生活の実際を紹介する実用ガイド。